自動車学校がなぜ「脳若」を?
石川県七尾市は人口5万4千人ほど。大きな市ではないが、天然の良港である七尾港を海の玄関口とし、能登の文化や経済の中心地として栄えてきた由緒ある場所だ。
この「森の中へ~七尾自動車学校」という緑色の素敵な本が送られてきたのはつい最近の事。
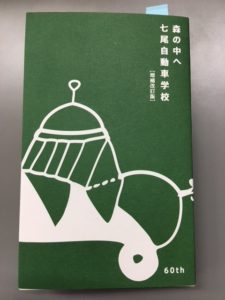
創立60周年の記念として発行されたこの本には深い歴史と思いが詰まっているなと感じる。第2章では交通教育事業と共に~「脳若」で地域の懸け橋に~・・・のくだりもあり、『地域の高齢者の生活の質を維持・向上させ、「脳若」の輪を七尾自動車学校から広げていこう』という一文もある。
事業計画の中にしっかりと「脳若」の文字を見つけられたことは、本を読み進めていくうちに嬉しくもあり、同時に改めて責任も感じる。
本の中には昨今のAIによる「自動運転」への危機感にも触れられている。高齢化と人口減少でこの業界は切実だと想像できるし、生き残りをかけて地域密着で何をしていくか?は常に最重要課題で考えていらっしゃると思う。人が運転しなくて良い時代となれば、「自動車学校」という文字から「自動車」がなくなり、「学校」だけが残る、と。
「学校」は学ぶ意欲のあるものが集う「コミュニティ」であるから、そのカリキュラムがあれば「自動車」という言葉にしばられずに事業を展開できるのではないか、という文章もみつけた。「脳若」で個人、企業に必要とされる講座を提供できれば人材育成を含め、幅広い事業展開が可能になるということだ。
「自動車学校」という強みを生かし自治体とコラボ
さて、12月21日の北国新聞にようやく七尾自動車学校の「脳若事業」の始まりともいえる記事が掲載された。

中能登町高齢者支援センターでは「冬にあまり外出せずにいたら、春に外に出る気がなくなった」という相談をうけたことで毎冬に予防教室を開いてきたという。ここに地元の自動車学校とのコラボが成立した。
ここまで到達するまでに、地域での脳若単発講座が何回も開催され、講師は場数を踏んできている。

思い出に残っているのは、「脳若」で今後の展開をどうしていくか?を鹿児島県の錦江町役場へ向かう車中で錦江湾見ながら中能登町の福祉課担当様と長々と電話で話をしたこと。鹿児島の陸の孤島(失礼(^^;))ともいえる場所から、これまた能登の福祉課の担当と話している状況がとても不思議で、今でも会話が印象に残る。私があまりにも一生懸命話すので圧倒されてた感があったが、 伝わっているな、というのは電話口でも感じることができた。「脳若」にかけてみよう、と思ってくれたのを感じた。
まずは、予防講座の開催でしっかりと「脳若」の認知度を能登で広めたら、次は担い手の育成。やらなくてはならないことは山積みだと思うが、今はSNSやネットの時代。福岡で展開している事例をしっかりと伝授させていただきたいと心から願っている。
地域づくりは人づくり。地域の事は地域の事業者が入り込んでやるべきだと思うし、地域の資源(元気高齢者の活用含め)を掘り出すのは地域住民でないとできない。今後のさらなる展開をしっかりとイメージしていきたい。
____________________
★1月のセミナー
1月20日(東京)1月21日(大阪)
動画セミナーはいつでもご視聴になれます。
情報はこちらからご覧ください。

